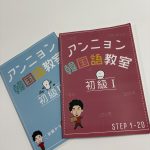45歳のときからチェロを習い始め12年が経っんだけど、いまだに先生には「音楽になっていない」と言われてしまいます。
音楽というのは、一つ一つの音符がつながってフレーズになり、そのフレーズが重なって音楽になるんだけど
自分の演奏は、一音一音にこだわりすぎて、全体の流れが途切れてしまっているそうです。
目標に向かって走るとき、目線をあげてゴールを見ながら勢いを保てばいいのに、足元ばかり見て一歩一歩を置いてしまう──そんな感じらしいです。
もし正確に音符を再現するだけで美しい演奏ができるのなら、AIに弾かせた方が上手いはず。
だけど、多分AIの演奏には、人の心を動かせる【生きている感じ】がない様な気がします。
少なくとも自分の演奏には、人を笑わせるくらいの“人間らしさ”はあるから、そこはAiに負けてないと思ってます。
そう考えると、「音楽」と「命のあるもの」はどこか似ているような気がします。
最近は、健康の為にと、大豆を脱脂して、たんぱくを抽出して強い酸で分解 精製して乾燥させアミノ酸というサプリメントにして食べる人も多いけど、自分にはその行為が音符をバラバラにして音楽の構造だけを見ようとしているようにも見えてしまいます。
大豆は命の塊で豆腐や納豆、味噌などいろんな料理に変われる万能選手なのに、わざわざ分解して命を失わせてしまう。
自分も昔、ウエイトトレーニングに熱中していた頃はアミノ酸を飲んでいたんだけど、まるで車にガソリンを入れるような感覚で栄養を流し込んでいたから、今思えば、それは“命の補給”ではなく“効率の追求”だった様な気がします。
当時は納豆より市販のサプリメントの方が完全に近い食材だと信じていました。
ヨガを始めてから、自然な食べものを味わう方が体と心を満たせる様な気がして、今は自分の唾液の力や酵素、咀嚼や消化の力を信じて、タンパク質は料理して食べるようにしています。
空腹の野生動物の前にサプリメントを置いても見向きもしないのは、きっと動物達が求めているのが“命”だからなんじゃないかなと思ってます。
ウェイトトレーニングが大好きだった頃の自分が飲んでいたのは、栄養補助食品ではなく、エゴ補助食品で、当時は体ファーストではなく理屈ファーストでした。
丁寧に調理された食事には温かさや香りがあり、舌にも心にもやさしく、食べながら、何かしら感情が動きます。
その食材を化学的に分解して錠剤にしてしまうと命が消え、残るのはただのデータだけになってしまう気がします。
メンデルスゾーンがこんな事を言ったそうです。
「モーツァルトの旋律を理屈で解き明かそうとした瞬間、音楽は死んでしまう」
命も芸術も、理屈を超えたところにこそ息づいているのだと思います。
学生の頃のメンデルスゾーンは、先生に「この音楽は理論的に間違っている」と指摘されても「だけど、耳には心地よく聞こえます」と反発したそうです
いつか、自分も人の心を動かせるチェロ弾きじいさんになりたいから
その日のためにも命を補充して、命のある音を探していこうと思っています。